職場で後輩や部下が「そうそうそう」と言う場面、意外とよく見かけませんか?上司の話に相づちを打つようでいて、どこか急いでいるような、適当にあしらっているような…そんな印象を受けたことがある人も多いはずです。
今回は、目上の人に対して「そうそうそう」を口癖のように使う部下や後輩の心理と、その言葉が周囲に与える印象について解説します。実はその一言、相手を気遣っているようでいて、自分を守るための“防御反応”かもしれません。
上司や先輩に対して「そうそうそう」と言うときの心理
後輩が目上の人に「そうそうそう」と言うとき、そこには慎重に選ばれた“言葉のバリア”が隠されています。
早く話を終わらせたい
内心では「もうその話、わかってるし、終わらせたい」と思っているけれど、露骨に遮るわけにはいかない。そんなとき、部下は「そうそうそう」と共感を装って会話を切り上げようとします。
うわべだけ合わせて角を立てないため
「なるほど」「はい」では物足りないけれど、本気で共感しているわけでもない。そんな微妙な距離感を保つために「そうそうそう」が使われます。これは、意見が異なっても正面からぶつからない“やんわり回避”のテクニックでもあります。
緊張してテンポを合わせようとしている
目上の人との会話に緊張して、沈黙が怖くて「そうそうそう」と反射的に出ることも。実際には深く理解していなくても、テンポを合わせることでその場を乗り切ろうとしています。
口癖としての「そうそうそう」:部下や後輩の性格傾向
この口癖を頻繁に使う後輩には、以下のような性格傾向が見られることがあります。
空気を読みすぎるタイプ
周囲の雰囲気に敏感で、少しでも角が立つことを避けようとします。その結果、「とりあえず共感」的な表現として「そうそうそう」を選びがちです。
自己主張が苦手
本音では違う意見を持っていても、目上の人に逆らうことを避け、「そうそうそう」で流す傾向があります。「異議を唱えるのが怖い」「波風を立てたくない」という心理が背景にあります。
面倒な会話を早く切り上げたい
上司の昔話や説教、長い説明に対して「はい、はい、わかってます」と言いたい気持ちを、やんわりと「そうそうそう」で表現しています。やや“受け流し”のニュアンスが含まれます。
こんな場面で「そうそうそう」が使われやすい
具体的にどんな職場シーンでこの口癖が出やすいのか、よくあるパターンを紹介します。
面倒な説明が始まったとき
「この書類はこうやって、こういうフローで…」「あ、そうそうそう、前に教えてもらいました」など、すでに知っている情報だと感じたときに、時間短縮のために使われます。
説明するのが面倒なとき
せんぱい:「このシステムの操作方法を教えてほしい」
後輩 :「いいですよ。これは〇〇して、次に〇〇して・・・」
せんぱい:「ここが難しいから、この部分だけもう一度教えてほしい」
後輩 :「ここは〇〇して、次に〇〇して・・・」
せんぱい:「理解できた。ここは〇〇して、次に〇〇するんだね?」
後輩 :「そうそうそう」(こころのつぶやき「あー教えるのめんどくせー」)
目上の人から見た「そうそうそう」の印象とは?
部下の「そうそうそう」に対して、上司や先輩はどんな印象を持つのでしょうか?
ポジティブな印象の場合
- 話を理解してくれているように感じる
- テンポが良く、会話がスムーズに進む
- 共感してくれていると錯覚しやすい
場の雰囲気が良ければ、「話のわかる若手だな」と好印象を与えることもあります。
ネガティブな印象になる場合
- どこか軽く流されているように感じる
- 本当に理解しているのか不安になる
- 社交辞令っぽくて信頼しにくい
特に「そうそうそう」が口癖のように多用されると、誠意が感じられず、逆に不信感を持たれることもあります。
エピソード
会議の後、上司が新しいプロジェクトの進め方について熱心に語っていました。すると若手社員の佐藤さんが「そうそうそう」と相づちを打ちながら、うなずいています。一見すると理解を示しているようですが、その表情にはどこか焦りの色も。実は佐藤さん、頭の中では「もう大体わかっているから早く次に進みたい」と思っていたのです。
この「そうそうそう」は、相手を遮らずに会話を切り上げたいときのサイン。上司の説明を軽く流しているようにも聞こえますが、本人にとっては“波風を立てずに進める処世術”でもあります。
ただし、使い方を誤ると、軽く流されていることに気づいた上司が不快に感じたり、怒る可能性もあるので気を付けたいところです。
まとめ
部下や後輩が「そうそうそう」と言うとき、そこには単なる共感以上の心理が隠れています。会話を早く終わらせたい、無難に流したい、波風立てたくない…そんな思いや処世術が、その一言に詰まっているのです。
上司や先輩からすれば、軽く聞こえてしまうリスクもありますが、背景を理解すれば、若手なりの“気遣い”のかたちと捉えることもできます。次に誰かが「そうそうそう」と言ったとき、その言葉の奥にある本音を、少しだけ想像してみてはいかがでしょうか。
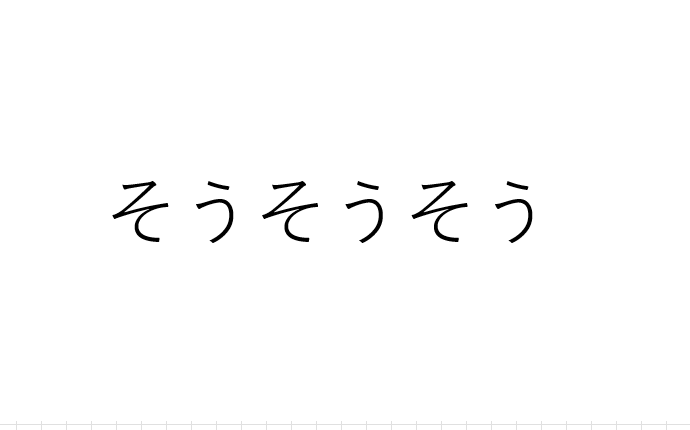

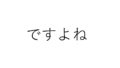
コメント