「すみません」という口癖は、礼儀正しさや謙虚さを表現する一方で、聞く人によってはイライラの原因となることがあります。
この言葉が頻繁に使われる背景には、話し手の心理的な側面が深く関わっています。
なぜ「すみません」がイライラを引き起こすのか、そしてその背後にある心理は何なのかを探り、より健全なコミュニケーションを目指すヒントを見つけましょう。
ちなみに、皆さんは口癖を言う側でしょうか?ご自身の口癖で嫌になった経験がある方に共感して頂ける、書籍の紹介記事もあります。あわせて読んで頂くと、より口癖への理解が深まります。
「すみません」口癖が引き起こすコミュニケーションの問題

過剰な謙虚さと自己否定
「すみません」と頻繁に口にすることは、話し手が過剰な謙虚さや自己否定の感情を抱えていることを示す場合があります。
この過剰な自己否定は、聞き手にとって話し手が自信を持っていないように感じさせ、コミュニケーションの効果を低下させる可能性があります。
責任の過剰な受け入れ
「すみません」の多用は、話し手が責任を過剰に受け入れていることの現れであり、必要以上に謝罪することで、聞き手を不快にさせることがあります。
これは、話し手が他者からの評価を過度に気にしていることを示している場合があります。
不必要な謝罪の連鎖
頻繁な「すみません」は、不必要な謝罪の連鎖を引き起こし、コミュニケーションの流れを妨げます。
この口癖によって、本来必要のない場面での謝罪が行われ、会話の自然な流れを阻害することがあります。
コミュニケーションの受動性
「すみません」という言葉の多用は、話し手の受動的な態度を示すことがあり、これが聞き手にとってイライラの原因となることがあります。
聞き手は、話し手が主体的な態度を欠いていると感じることがあります。
「すみません」口癖に対する理解と対策

背景にある心理の理解
「すみません」という口癖の背後には、話し手の不安や自己評価の低さが潜んでいる可能性があります。
これを理解することで、聞き手は話し手の立場に共感し、イライラする感情を和らげることができます。
コミュニケーションスタイルの改善
話し手自身がこの口癖に気付き、コミュニケーションスタイルを改善することも重要です。
具体的なフィードバックや、自信を持って話す練習を通じて、必要以上の謝罪の言葉を避けることができます。
相互の理解と尊重
「すみません」という口癖に対してイライラする人は、相手の言葉の背後にある心理を理解し、相互の尊重に基づくコミュニケーションを心がけることが大切です。
相手の不安を理解し、安心感を与えるような応答をすることが、コミュニケーションの質を向上させます。
環境の改善とサポート
職場や家庭など、コミュニケーションが行われる環境を改善し、話し手が自信を持って意見を表現できるような支援を行うことも有効です。
安心して自己表現ができる環境を整えることが、過度な謝罪の減少につながります。
他人を理解しようとするのには限界がある
「すみません」と口にしてしまう人の心理や、コミュニケーションのコツについて説明してきました。
結局のところ人は簡単には変わりませんし、周囲のサポートがあったとしても限界があります。
「すみません」という言葉を受けてイライラする自分を変えるほうが、よっぽど効率的だと考えます。
いわゆる認知を変える、ということです。
例えば書籍などの身近な情報から、少しづつ取り組んでみることをおすすめします。
エピソード
「すみません」が減ったら、職場の雰囲気が変わった
佐藤さん(30代・会社員)は、職場で何か頼まれるたびに「すみません」と言うのが癖になっていた。
「佐藤さん、今日の会議の資料、まとめてくれる?」
「すみません、すぐやります!」
「この案件の進捗、ちょっと確認してくれる?」
「あっ、すみません!すぐ確認します!」
特に悪気があるわけではなく、むしろ礼儀正しくいたいという気持ちからの口癖だった。でも、ある日、同僚の鈴木さんに言われた。
「佐藤さん、そんなに謝らなくてもいいよ。仕事なんだから当然のことをやってるだけでしょ?」
その言葉にハッとした。たしかに、頼まれごとに対して「すみません」と言う必要はない。むしろ、「了解です!」「わかりました!」と返したほうが、ポジティブな印象を与えるのでは?
それから佐藤さんは、「すみません」を減らす努力を始めた。
「佐藤さん、この件、お願いできますか?」
「はい、承知しました!」
「これ、ちょっと修正してもらえる?」
「了解です!すぐにやりますね!」
すると、職場の雰囲気が変わってきた。周囲も佐藤さんの明るい返答に、より気軽に話しかけるようになり、頼まれることが苦痛ではなく、チームワークの一環のように感じられるようになったのだ。
以前は「すみません」と言うたびに、「私が悪いのかな?」と無意識に感じていた。でも、前向きな言葉に変えたことで、自然と自信を持って仕事に取り組めるようになった。
言葉ひとつで、仕事のモチベーションや人間関係は大きく変わる。「すみません」を減らしたことで、佐藤さんは仕事の場面でもより前向きになれたのだった。
まとめ
「すみません」という口癖がイライラの原因となる場面では、その背後にある心理的な要因を理解し、相互の理解と尊重に基づいたコミュニケーションを目指すことが重要です。
話し手と聞き手双方が意識を改め、コミュニケーションスタイルの改善に取り組むことで、より健全で効果的な関係構築へと繋がるでしょう。

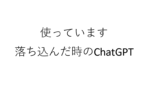


コメント