多くの人が無意識のうちに使用する「でも」という言葉。
しかし、この小さな接続詞が私たちの心理状態について、どのようなヒントを与えているのでしょうか?
このブログでは、「でも」の口癖が持つ心理的背景とその影響について掘り下げていきます。
ちなみに、皆さんは口癖を言う側でしょうか?ご自身の口癖で嫌になった経験がある方に共感して頂ける、書籍の紹介記事もあります。あわせて読んで頂くと、より口癖への理解が深まります。
「でも」の口癖が示す心理的意味

不確実性の表現
「でも」の口癖は、しばしば意思決定時の不確実性や迷いを表します。
人が決断を下す際に「でも」と言うことは、内心ではまだ完全に納得していない、あるいは他の選択肢についても考えていることを示唆しています。
対立を避ける姿勢
対話中に「でも」と頻繁に使用する人は、対立を避け、和解を図る傾向にあることを示すことがあります。
この口癖は、相手の意見に配慮しつつも、自己の見解を優しく提示したいという心理から来ている場合が多いです。
自己表現の難しさ
自分の意見や感情を直接的に表現することが難しいと感じる人々は、「でも」という言葉を介して間接的に自己表現を試みることがあります。
これは、自己防衛機制の一形態とも解釈できます。
内向的な性格の指標
「でも」を口癖として頻繁に使うことは、内向的な性格の指標となることがあります。
内向的な人々は、対外的なコミュニケーションよりも内省と深い思索を重視するため、このような表現が現れやすいのです。
「でも」の口癖が与える影響

コミュニケーションの障壁
「でも」という言葉は、対話を停滞させる可能性があります。
相手はこの言葉を否定的なサインと受け取り、防御的な姿勢をとることがあるため、スムーズなコミュニケーションを妨げることになります。
関係性の構築における課題
対人関係の構築において、「でも」という言葉の使用は、相手に対する不信感や不安を引き起こすことがあります。
これは、長期的に信頼関係の構築を難しくする可能性があります。
内省と自己発見のチャンス
一方で、「でも」の口癖を持つ人は、自身の不安や迷いを深く理解し、それを克服するための内省のきっかけとすることができます。
自己認識を高めることは、個人的な成長に繋がります。
柔軟性の表れ
また、すべてが否定的なわけではありません。
「でも」という言葉の使用は、柔軟な思考を示し、異なる視点を受け入れる能力のある人物を表すこともあります。
口癖「でも」をうまく扱う方法

意識的な使用
「でも」という言葉を使用する際は、その背後にある意図を意識的に考えることが重要です。
自分の本当の意見や感情を正確に伝えるための工夫をしましょう。
自己反省の習慣
自分の口癖がどのような影響を与えているかを理解し、自己反省の習慣を身につけることが、コミュニケーションスキルの向上に繋がります。
相手の視点を尊重
対話中に「でも」と言う前に、相手の視点を十分に考慮し、理解しようとする姿勢を持つことが、関係性の改善に役立ちます。
エピソード
「でも」が止まらなかった新人時代の話
Yさん(30歳・会社員)は、新卒で入社した頃、先輩からのアドバイスに対してつい「でも…」と言ってしまう癖があった。
ある日、資料作成のやり方について先輩のKさんが教えてくれた。
「Yさん、この資料、もう少し簡潔にまとめたほうが分かりやすくなるよ。」
「でも、上司に前回 ‘詳細に書くように’ って言われたので…。」
Kさんは「なるほどね」と言いながらも、少し困った表情を浮かべた。
その後も、何か指摘されるたびにYさんは無意識に「でも…」と返してしまった。
「このフォント、大きくしたほうが見やすくなるよ。」
「でも、こっちのほうがカッコよく見えるかなと思って…。」
「このメール、もう少し柔らかい表現のほうがいいかもね。」
「でも、丁寧すぎると回りくどくなるかもって思って…。」
すると、Kさんが優しく言った。
「Yさん、 ‘でも’ って言葉、無意識に使ってない?」
Yさんはハッとした。自分では意見を伝えているつもりだったが、Kさんからすると「せっかくアドバイスしても否定されているように感じる」こともあるのだと気づいた。
Kさんは続けた。
「 ‘でも’ を ‘そうですね’ に変えてみると、会話の雰囲気がガラッと変わるよ。」
次の日から、Yさんは意識して「でも」の代わりに「なるほど」「そうですね」と言うようにしてみた。
「この資料、簡潔にしたほうがいいよ。」
「そうですね、どの部分を削るのが良さそうですか?」
「このフォント、大きいほうがいいかも。」
「なるほど、大きくしたらどう変わるか試してみます!」
すると、先輩たちの反応が変わった。以前よりアドバイスを受け入れやすくなり、会話もスムーズに進むようになった。
Yさんはこの経験から、「 ‘でも’ は考えを整理するために必要な言葉だけど、使いすぎるとコミュニケーションの壁になってしまうこともある。」 と学んだ。
もし、あなたの周りに「でも」が多い人がいたら、それは決して否定ではなく「自分の意見を大切にしたい」という気持ちの表れかもしれない。そんな時は、相手の考えを尊重しながら会話を続けると、より良い関係が築けるかもしれない。
まとめ
「でも」という口癖は、私たちの心理状態やコミュニケーションスタイルに大きな影響を与えます。
この小さな接続詞を通じて、自己表現や対人関係における深い洞察を得ることができます。意図せずとも、私たちの不安や迷い、そして対立を避けるための願望が「でも」という言葉に込められているのです。
しかし、この口癖を意識的に管理し、より効果的なコミュニケーション方法を探求することで、自己成長に繋がり、より健全な人間関係を築くことができます。
自分自身の言葉遣いに注意を払い、その背後にある心理的意味を理解することは、自己認識を深める素晴らしい機会です。
また、相手の言葉遣いからも、その人の内面や心情を読み取ることができます。「でも」という言葉が頻繁に使われる場面を観察することで、相互理解とコミュニケーションの質を高めることができるのです。
言葉一つ一つが持つ力を理解し、それを自己成長と人間関係の改善に役立てることで、私たちはより充実したコミュニケーションを享受できるようになるでしょう。

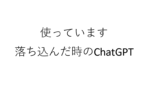


コメント